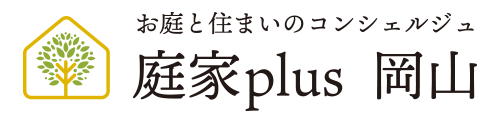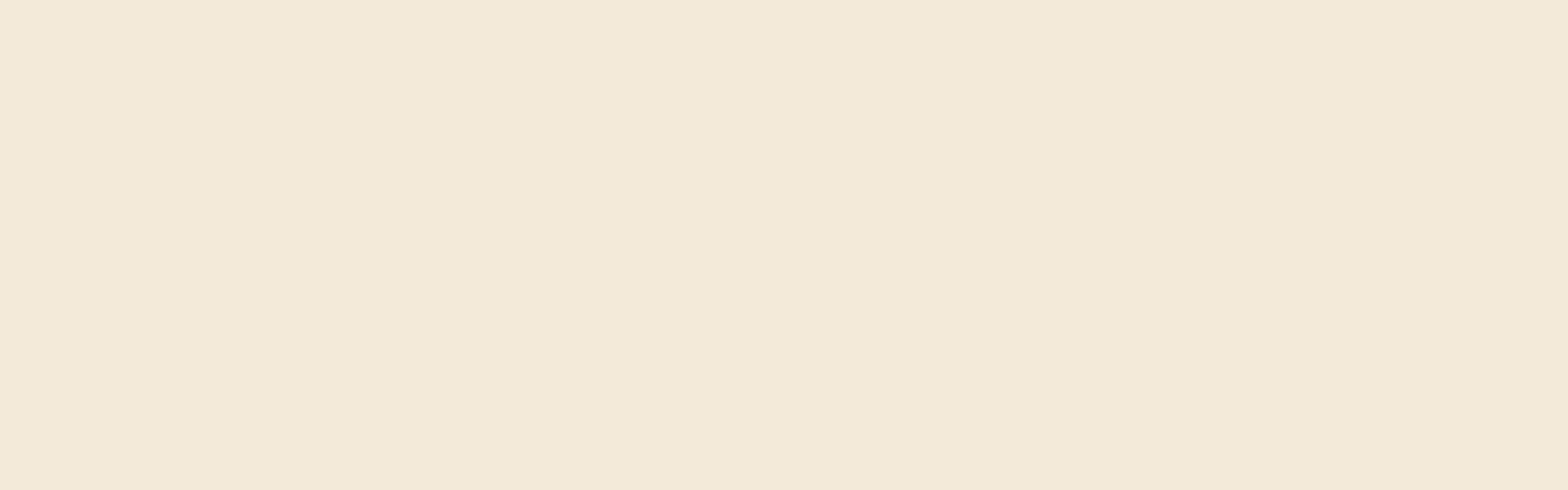庭木の剪定・伐採の豆知識です
-

【ハナカイドウ(花海棠)】剪定の基本を庭師が伝授
短い枝を出させ花数を増やす剪定 「ハナカイドウ(花海棠)」は、リンゴの花に似た美しく、可愛らしい花を春に咲かせる落葉樹です。濃い紅色から淡い色へと変化する花を枝いっぱいにつけ、庭植えのほか、鉢花や盆栽としても人気のハナカイドウはお庭のシン... -

【マンサク(満作)】剪定の基本を庭師が伝授
美しい枝ぶりを保つ剪定! 早春に咲く黄色い小花がさわやかな「マンサク(満作)」。名前の由来のひとつに、他の花に先じて「まず咲く」が東北地方でなまって「マンサク」と名付けられたという説があります。白い幹肌にさわやかな緑の葉が美しく、秋には葉... -

【バイカウツギ(梅花空木)】剪定の基本を庭師が伝授
株を更新し花つきをよくする剪定 古くから庭木として親しまれてきた「バイカウツギ(梅花空木)」は、名前の「梅花(バイカ)」の通り、ウメに似た香りのよい白い花を初夏に咲かせる落葉性の花木です。日本では本州以南の山野に自生しています。バイカウツ... -

【ムラサキシキブ(紫式部)】剪定の基本を庭師が伝授
「ムラサキシキブ(紫式部)」は、秋に紫色の可愛らしい実がなる樹木です。細い枝が密に茂って株立ちとなり、葉は秋に紅葉し、実は球形で美しい紫色に熟します。和風や和モダンのお庭や、雑木のお庭の根締めやグランドカバーとして利用されることが多くあ... -

【ゲッケイジュ(月桂樹)】剪定の基本を庭師が伝授
ゲッケイジュ(月桂樹)の剪定!剪定のプロが方法を伝授します ローマ時代からアポロンの聖樹として神聖視されたゲッケイジュ(月桂樹)の剪定に失敗しないために、庭.proの庭師が剪定方法をレクチャーいたします。ゲッケイジュ(月桂樹)の剪定は3月~4月... -

【ムクゲ(木槿)】剪定の基本を庭師が伝授
朝開いて夕方しぼむ大輪の一日花が3カ月以上にわたって夏から秋のお庭を彩る「ムクゲ(木槿)」は、花色もピンク、白、紫、紅、花形も一重や半八重、八重とさまざまで、たくさんの園芸品種があります。ほかの樹種との混植に向いていて、暑さや寒さ、乾燥に... -

【ラベンダー】育て方の基本を庭師が伝授
優雅で豊かな香りがすることから、人気のラベンダー。でも放置している木質化してしまう成長の非常に早い植物です。強壮や鎮静、体の不調を整える効果が期待できることから、昔は薬用植物として使われていました。ラベンダーは種類も多いのでそれぞれ育て... -

【ヤマブキ(山吹)】剪定の基本を庭師が伝授
「ヤマブキ(山吹)」は万葉集にもその歌が詠まれているほど古くから庭木として利用されている、日本では馴染の深い樹木です。春から初夏にかけて花を咲かせます。その花は「やまぶき色」という言葉があるように、とても鮮やかな黄色をしています。樹高は... -

【サカキ(榊)】剪定の基本を庭師が伝授
弱めの剪定であれば1年中いつしても問題なし いつもスーパーなどで購入して神棚にお供えしているサカキ(榊)を自宅の庭で育てれば便利だし何より経済的!ただ昔の人はサカキ(榊)は神木だから位の高い神官のような家にしか植えてはいけない・・・・そん... -

【ヒバ】剪定の基本を庭師が伝授
生垣用途や庭木として人気のヒバ。特に手入れをしなくても枯れることがなく、ぐんぐん成長していくことから根強い人気を誇ります。その一方で育ちすぎて手にあまることもありますので、最低でも年に1回は剪定することがおすすめ。ここではヒバの木の特長や... -

【ボケ(木瓜)】剪定の基本を庭師が伝授
古くから日本の人々に愛されてきた「ボケ(木瓜)」は、花と実が楽しめる日本を代表する花木です。春には花を咲かせ、夏に香りのよい黄緑色の実をつけます。暑さ寒さに強く、洋風、和風問わずシンボルツリーや生垣に使用されています。放っておくと枝がか... -

【シラカシ】剪定の基本を庭師が伝授
庭木で人気のシラカシ!剪定や成長に合わせてお手入れ解説 庭木で人気のシラカシ、1年中緑の映えるカシ(樫)の木の一種で、公園や街中でも見かけることも多く、私たちにとっても身近な樹木ですよね。その黒みがかった幹の色から、別名「クロカシ」とも呼...